生活保護を受けるには?

病気やケガ、失業などで生活が厳しくなった時、あなたは一人ではありません。
生活保護制度は、そんな困っているあなたを支えるための国の制度です。
このページでは、生活保護について、「どんな人が受けられるの?」「どんな手続きが必要なの?」といった疑問にわかりやすくお答えします。生活保護の受給を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
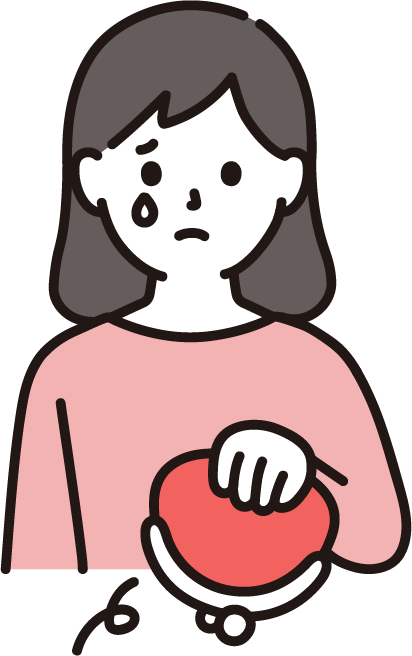
生活保護制度とは
生活保護は、人として最低限必要な生活を保障するものであり、人権尊重の観点からも重要な制度です。日本国憲法第25条では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」ということを保障しています。生活保護制度は、この憲法の理念を実現するための制度です。つまり、経済的な理由で生活が困難になった場合、誰もが生活保護を申請し、国の支援を受ける権利を持っているということです。
病気、ケガ、失業など、様々な理由で生活が困難になった場合、食費・光熱費・家賃・医療費など、生活に必要な費用が支給されます。
受給資格の条件
生活保護を受給するための絶対条件は、申込者の世帯収入が居住地の最低生活費よりも低いことです。
生活保護の最低生活費は、世帯の人数や年齢、地域などによって異なります。これは地域によって物価や家賃相場が異なるため、どの地域で生活保護を受給しても平等な生活を送る為に最低生活費は地域によって変動するためです。
おおまかな条件は以下の通りです。
詳細な受給資格の条件や、最低生活費を知りたい場合は、お住まいの地域の市区町村の福祉事務所に相談してください。
①収入が低いこと
世帯の収入が、厚生労働大臣が定める最低生活費を下回っている必要があります。無職の人はもちろん、働いている人も収入が少ない人ほど生活保護の受給資格を得やすいということです。収入には給料の他に、資産・土地・貯金・年金・保険金・仕送りなども含まれます。
②資産が少ないこと
預金、不動産、自動車など、生活に必要な費用に充てることができる資産が一定額以下である必要があります。利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、例外的に保有が認められる場合があるのでまずはご相談ください。
③働けない状態であること
病気、ケガ、高齢、障害などで働くことが困難な状態である必要があります。ただし、働ける状態にある場合は、求職活動を行いながら生活保護を受給することが求められます。乳幼児を育てているシングルマザーや親族の介護など、本人が元気でも働けない事情がある場合には生活保護の対象になります。働ける状況に戻った際、申請をせず受給を続けた場合、減額や受給停止になりますのでご注意ください。
④親族からの援助が期待できないこと
親族から経済的な援助を受けることができる場合、生活保護よりも親族からの援助が優先されます。ただし、親族からの援助を駆使しても最低生活費を下回っている場合は受けることが可能です。また、申請者の親族に扶養できるか扶養照会を行い、拒否された場合は生活保護を受けることが可能です。虐待やDVなど、扶養照会をすることで危機にさらされてしまうケースには扶養紹介を断り、生活保護を受けることも可能です。
支給される支援
生活保護では以下の8つの扶助があります。年齢、健康状態等、個人や世帯の生活状況を考慮して1つまたは複数の扶助が支給されます。
①生活扶助
食費、衣服費、光熱水費など、日常生活に必要な費用を支給します。生活保護の最も基本的な扶助です。
②住宅扶助
家賃や住宅の修繕費などを支給し、住居を確保するための支援を行います。
③医療扶助
医療費の自己負担分を免除し、必要な医療が受けられるようにします。
④介護扶助
要介護状態にある人が、介護サービスを安価に利用できるようにします。
⑤教育扶助
義務教育に必要な費用を支給し、子どもたちが安心して学校に通えるようにします。
⑥出産扶助
出産に必要な費用を支給します。
⑦生業扶助
就職活動に必要な費用や、職業訓練を受けるための費用を支給し、自立を支援します。
⑧葬祭扶助
死亡した世帯員のための葬儀費用を支給します。
受給までの流れ
生活保護の申請は居住地の市町村役場、特に社会福祉課で行います。以下のステップで進められます。
①福祉事務所への相談
お住まいの地域の市区町村の福祉事務所に相談しましょう。福祉事務所の窓口で「生活保護の相談をしたい」と伝えれば、担当のケースワーカーが対応してくれます。
②必要書類の提出
収入証明書、資産証明書、健康保険証など、ケースワーカーから指示された書類を準備し、提出します。必要に応じて医師の診断書などが必要になる場合もあります。
③調査
申請後、役場の職員があなたの自宅を訪問し、生活状況・収入・支出・病気やケガなど、申請者の生活状況や財産状態を調査します。
④審査
福祉事務所では、提出された書類や聞き取り調査の結果をもとに、あなたの生活状況が生活保護の基準に合致しているか審査を行います。主に収入と資産の審査、働ける状態かどうか、扶養照会などを審査します。
⑤決定通知
審査の結果、生活保護の受給が認められる場合は、決定通知が送られます。通知には、支給額や支給開始日などが記載されています。
⑥受給開始
決定通知に記載された日から、生活保護の支給が開始されます。
生活保護受給者の義務について
生活保護は、経済的に困窮している人が、健康で文化的な最低限度の生活を営めるよう、国が支援する制度です。しかし、この制度を受けるには、受給者にもいくつかの義務が課せられています。
①勤労の義務
働ける状態にある場合は、自分の能力に応じて働かなければなりません。仕事を探し、働くための努力をすることが求められます。
②支出の節約
生活費を無駄遣いせず、節約に努めなければなりません。生活保護費は、最低限の生活を維持するためのものです。
③指示・指導への協力
福祉事務所の職員からの指導や指示に協力し、自立に向けて努力しなければなりません。職業訓練や就労支援などのプログラムに参加することが求められる場合もあります。
④資産の活用
預金や不動産など、利用できる資産がある場合は、生活費に充てることが求められます。
⑤扶養義務者の援助
親族に扶養義務がある場合は、その援助を受けるよう努めなければなりません。
⑥報告義務
収入や資産の状況に変化があった場合は、速やかに福祉事務所に報告しなければなりません。
義務を怠った場合は
これらの義務を怠った場合、生活保護の支給が停止される可能性があります。また、不正受給とみなされ、刑事罰に問われることもあります。
生活保護は、国民の権利でありながら、同時に国民の税金で支えられています。そのため、受給者には、自立に向けて努力し、社会の一員として責任を果たすことが求められます。
まとめ
生活保護は、一時的な生活の困窮を乗り越えるための制度です。受給者は、これらの義務を果たすことで、自立を目指し、社会復帰を目指すことが期待されています。
この記事が、生活保護についてより深く理解するための参考になれば幸いです。
生活保護に関する疑問や不安な点があれば、遠慮なくお住まいの地域の福祉事務所にご相談ください。


